文化社会学 or 文化政治学
こういった形で社会的な事象を広く扱うので、カルチュラル・スタディーズを文化社会学というように表現する人たちもいます。そういった表現もあながち間違いではありません。しかしながらより正しく言うならば、「文化政治学」だというべきでしょう。なぜなら、カルチュラル・スタディーズは広い意味での文化や社会を読み解くさいに、どのような政治性、権力関係がその中に潜んでいるのかということを常に問題意識として持っているからです。
パーソナル・イズ・ポリティカル
皆さんの多くが政治という言葉からは、首脳会談や国家間の軋轢や摩擦に代表される国際関係であるだとか、国会で繰り広げられる与党と野党の攻防戦などが繰り広げられる舞台のようなものを連想されると思います。そういう風に考えると、政治なんて自分とは関係のない世界のことだ、と短絡的に考えがちです。

しかしながら、「パーソナル・イズ・ポリティカル(Personal is political.)」、個人的なことは政治的である、という表現があります。つまり、社会や集団の中で生活している以上、私たち個人はさまざま政治的な力関係から自由なことなどまずありえないのです。
このような狭い教室においても、それは言うことができるはずです。このサークル、○○○○の長である、■■■君は、この集団の中で一定の権力を行使できる立場にあるでしょうし、その一方で、■■■君の抑圧に涙ながらに耐えているメンバーもいるかもしれません。醜いヒキガエルを腹いせに宅急便で彼の住所に送りつけてやろうか、などと悶々と考えている人さえいるかもしれません。
ともかく、ここで話をしている僕も、みなさんの貴重な時間を奪いつつ話をしているという意味では、ある種の権力を使い、なんらかの力においてみなさんに聞くことを強制していると考えることももちろんできます。また、みなさんは部長の■■■君が僕にこうやって話しをすることを依頼した手前、とりあえずは聞く振りをしなければならないという無意識の抑圧を感じているかもしれません。大学というせまい空間においては、教師は教室においては生徒に対して権力を持ちうるでしょうし、みなさんが就職して会社などで働き始めた後、その組織や経営者にとってみなさんがマイナスのことを行えば、雇用主は権力を行使するでしょうし、あなたは抑圧を受け、場合によっては法的に排除されることさえありえます。
そういった力関係や権力構造は、それぞれの社会的立場・年齢・経済的な貧富・ジェンダー(社会的な性差)・人種・宗教・民族などさまざまな材料によって規定されています。 そういった風に考えていくと、私たちが行うこと、語ること、すべてが、その時々の立場や権力関係からは自由になることなどほとんどあり得ないと言っていいはずです。つまり、「個人的なことは政治的」たりうるわけです。
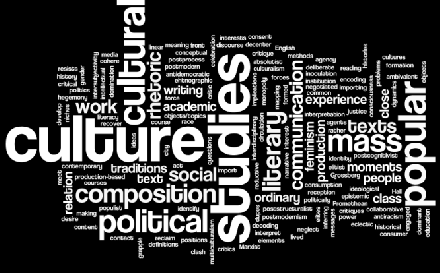
コメント